8世紀前半にウマイヤ朝勢力がその全域を支配して以来、このイベリア半島を統一したイスラーム勢力は存在しなかった。
ウマイヤ朝崩壊後はその生き残りが後ウマイヤ朝(コルドバのカリフ国)を建国するも、北方に侵出してきたキリスト教勢力と激しく争い、さらに1031年の後ウマイヤ朝滅亡後は、タイファと呼ばれるムスリムの小勢力たちによる戦国時代へと突入した。

史実ではその後、マグリブの新興勢力たるムラービト朝によってすべてのタイファが滅ぼされるも、この世界では違った。
タイファの1つであるアフタス家のバダホス王国が、1089年にアル=アンダルスを統一。

さらに勢力を北に拡大するこのバダホス王国に危機感を覚えたキリスト教勢力は、ローマ教皇アレクサンドル3世の号令の下、史上2度目となる十字軍を発令。

6万の軍勢がイベリアのイスラーム勢力に襲い掛かることとなる。


だが、これを救ったのが、「光輝王」ワハブ。

彼はそれまでの総指揮官であったタイタルが重傷を負い戦線を離脱した後に指揮を執り、偉大なるアフタスの王としての威厳を高らかに見せ、キリスト教勢力を駆逐していった。


そして1132年に十字軍は降伏を認め、イベリアから撤退。

その後残ったキリスト教勢力も併合していき、1139年についにワハブはイベリアの統一を宣言。イスバーニャ帝国と名を変え、自らもまた「征服王(ファティーフ)」を名乗ることとなった。


史実には存在し得なかった、イスラーム勢力による2度目のイベリアの統一。
不可能を可能にした征服王は、さらなる一大事業へと着手する。
すなわち、かつてのウマイヤ朝でさえも成し遂げられなかった、ヨーロッパへの進出。
「殉教者の道の戦い」のリベンジを、彼は今試みようとしていた。

アル=マンスールから始まる、アフタスの血族の物語はついに最終章を迎える。
果たして、一族の栄光の名は、いかにして世界に轟くことになるのか。
目次
Ver.1.12.4(Scythe)
使用DLC
- The Northern Lords
- The Royal Court
- The Fate of Iberia
- Firends and Foes
- Tours and Tournaments
- Wards and Wardens
- Legacy of Perisia
- Legends of the Dead
使用MOD
- Japanese Language Mod
- Historical Figure Japanese
- Nameplates
- Big Battle View
- Invisible Opinion(Japanese version)
- Personage
- Dynamic and Improved Title Name
- Dynamic and Improved Nickname
- Hard Difficulties
特殊ゲームルール
- 難易度:Very Hard
- ランダムな凶事の対象:プレイヤー含め誰でも

前回はこちらから
プロヴァンス戦役
1139年7月15日。ブルゴス。

かつて、このイベリア随一の王国を真に支配していた豪傑タイタルは、今際の際に瀕していた。
「ガニム・・・ガニムよ・・・おるか」


「ここに」
すでに目も見えなくなっている父の骨だけになった手のひらを掴み、タイタルの子ガニムは応える。

「おお、ガニムや・・・お前は、本当はこのイベリアの支配者と、なるはずであった・・・」
「ええ、ええ。御父上のお力でもって、確かに」
「しかし・・・しかしだ・・・後一歩のところで・・・それを邪魔された・・・。あの男・・・アミール・・・そしてその背後にいたであろう、忌まわしき王ワハブ・・・。
ガニムよ・・・決して許すでないぞ・・・我々は・・・我々の栄光を取り戻すためにも・・・アル=マンスールの一族を根絶やしにせねばならぬ・・・分かったな・・・」
父の言葉に、ガニムは無言で力強くその手を握り締めた。それでタイタルも安心したのか笑みを浮かべ、やがて寝息を立て始めた。
--------------------
「兄上」
ガニムが部屋を出ると、彼と父との会話を聞いていたであろう弟のシラジが不安気な様子で尋ねる。
「兄上は本当にアフタス家への謀反を行うおつもりですか?」

それを受けてガニムはちらりと部屋に視線を送り、無言のまましばらく廊下を歩く。部屋から十分に離れたところで、彼は弟に囁く声で応えた。
「そんなことが、できるわけがなかろう。今や、バダホス王国・・・いや、イスバーニャ帝国の皇帝陛下はこの地上における最強の存在。その叡智も類稀なるものなれば、これを打ち倒せる者などおるはずがない」

「我々にできることはただ忠誠を誓い、その褒賞を得られるようかしずくことだけだ」

「じゃあ兄上がここ最近、軍隊の準備をしているのは?」
シラジの言葉に、ガニムは深刻な顔つきで応える。
「うむ・・・近く、陛下は大いなる戦いへと赴く予定だ。すなわち、先の十字軍に対する復讐、我々イスラームの『ジハード』だ」

----------------------------
「情勢を、説明いたします」
帝国宰相を務めるプラビアのシャイフ、トーマス・メルカディエが地図を広げ、説明を開始する。

「半世紀前の内乱により、フランス王家のカペー朝は断絶。現在、王位についているのは国内の有力諸侯であったブロワ伯の系譜。ですが2代目のアルノーの死後、長子のエティエンヌが何者かに殺害され、後を継いだ弟のアンドレも『愚鈍』かつ病弱にて、その政治的基盤は揺るぎつつあります」




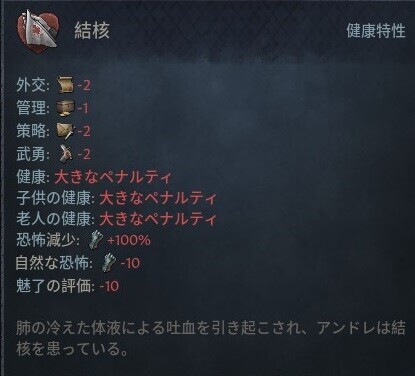
「事実それで国内では反乱が起こり、さらには隣接するジェノヴァ公国より侵略を受け、十分な対処ができていない状況」

「そんな状況を踏まえて南部のプロヴァンス辺境伯も独立を果たしているなど、ヨーロッパ最大勢力の一角たるフランスの状況は今や危機的なものとなっております」

「つまり、攻め時、ということだな」
皇帝ワハブの言葉に、トーマスは頷く。
「ならば、具体的にはどのように攻めるか」
「それは私から説明致しましょう」
ワハブの言葉に、若き帝国元帥のイーサが回答する。

「内乱と外患に苦しむフランス王国をすぐさま攻め込みたいところではございますが、そうなるとナバラ方面からの侵攻ルートを取らざるを得ません。
しかしその間、東のアラゴン方面からプロヴァンス辺境伯が反撃に出てくる恐れも御座います。次は自分たちの番だと、彼らも分かっているでしょうし、アラゴンの地は最近征服したばかりで我らへの忠誠心も高くはない」

「さすが、アラゴンの戦いの英雄は現地の状況を良く分かっていると言うわけか」
ワハブの言葉に、イーサは頷く。彼は先達てのアラゴン侵略戦争において英雄的な活躍を果たしたことで登用された男である。

![]()

「よって、私はまずはプロヴァンスへの侵攻を推奨致します。フランス王国は反撃でこちらに攻め込む余裕はないでしょうし、彼らはプロヴァンス辺境伯と違い、先の十字軍においても参戦を拒みましたからね」
「兵力差は?」
「問題ございません。敵方も同盟国を引き連れておりますが、こちらもマグリブやヒラールの同盟軍をあてにできる状況。総兵力においては敵軍を圧倒しています」

「さらに今であれば、プロヴァンス辺境伯は北方の同盟国のために兵を出している模様で、主力軍はほとんどこちらに残っていない可能性があります」

「よし――それでは、その作戦を承認しよう。全兵力を挙げ、ヨーロッパに侵攻せよ。我々の『復讐』の始まりだ」
--------------------
1139年9月20日。
イベリアを統一したばかりのイスバーニャ帝国は、続けて南フランスのプロヴァンス辺境伯へと宣戦布告。

ただちに1万弱の軍勢を展開し、各砦の制圧へと向かう。

プロヴァンス辺境伯軍も慌てて首都トゥーロンから兵を出すも、同盟国の戦争に主力を派兵している中で、出せる兵はわずか5,000超であった。

この軍勢を率いるのは、甲冑に身を包んだ一人の偉丈夫。
「――忌まわしき異教徒め。辺境伯不在の中、キリスト教世界を守るために、我々が何としてでもこれを防ぎ切らねばならぬ」

テンプル騎士団総長レオポルド。辺境伯領に残っていた兵士たちと自らの手勢をかき集め、異教徒の軍を撃退すべく、果敢に進軍していく。
その兵力差は圧倒的であった。かつてのトゥールの戦いでもキリスト教軍は数的劣勢ではあったが、今回はそれ以上の差である。

それでも、従軍する兵士たちの表情には悲愴さはなかった。彼らは皆、カリスマ的存在であるレオポルドの指揮の下、その命を全て棄てるつもりでいたのである。
「行くぞ――神は見ておられる。奇跡は我々の手で起こすのだ」
そして1139年11月27日早朝。
モンペリエの平原にて、両軍は激突した。

先に動いたのはキリスト教軍であった。騎兵も弓兵もいない彼らは、勇敢な騎士団を中心に一気に敵軍との距離を詰め、近づいていく。

イスラーム軍も弓兵の一斉射撃でこれに応えようとするも、全身を強固な甲冑に身を包んだキリスト教軍の騎士たちの前にほとんど効果はなく、至近距離まで近づいた彼らを、イスラーム軍も重歩兵を繰り出して迎撃を行う。

キリスト教軍は実に勇猛な戦いぶりであった。イーサも、その姿に信仰の垣根を超え、感銘を覚える瞬間もあった。最悪、押し切られる可能性もあると踏んだイーサは自ら前線に立ち味方を奮い立たせようと声を上げ、それがゆえに軽い傷を負う場面すらあった。

しかし数的かつ質的差は如何ともしがたく、イスラーム軍の後詰めも合流する中、太陽が中天にかかる頃には、キリスト教軍の大半が大地に倒れ伏しつつあった。


キリスト教軍の退却の号令が響き渡る。その瞬間を狙って、イーサは待機していたアブドラールと駱駝騎兵・カタフラクトの部隊に指示を送る。機動力に優れた彼らは一瞬にして退却しようとする敵兵を囲い込み、無防備なその敗残兵たちに容赦なく襲いかかり、その首を奪い取っていった。

最終的に、この「モンペリエの戦い」は、イスラーム軍による圧勝に終わったのである。


モンペリエの戦いの後、イスラーム軍は更なる勝利を積み重ねていく。
プロヴァンス辺境伯の同盟国として参戦してきていたアジャン伯の軍勢をトゥールーズにて撃破。


生き残りの兵を整え直し、ナヴァセルの地にて再戦を挑んできたテンプル騎士団の軍勢を再び壊滅させる。


これらの戦果を受け、1140年5月9日にはプロヴァンス辺境伯も降伏を受諾。

ラングドック地方のイスバーニャ帝国への割譲が認められ、帝国は欧州に対する橋頭保を獲得するに至ったのである。

そして、その間にフランス王国では国王アンドレが死去し、その弟でわずか19歳のジャスペールが王位に就く形に。

いまだジェノヴァ公国との戦争も続いているこの西欧の巨像の一角に、かつてイスラームに屈辱を与えたカール・マルテルの末裔国家に、いよいよ反撃を加えるべき時がやってきたのである。
フランス戦役
「準備が完了致しました」
元帥イーサの報告を受け、ワハブは頷く。
「兵士たちには立て続けの軍事行動を強いることになり、申し訳ないな」
「いえ。将兵たちはむしろ、この偉大なる遠征に対する強い誇りと興奮に満ちており、先のプロヴァンス戦役があまりにもあっけなく終わったことに物足りなさすら感じている者もおります」
「そうか。だが、今回は先の戦いよりも気を引き締める必要はあるだろう」
「ええ」
皇帝の言葉に、イーサは真剣な表情で頷いた。
「今回の遠征はより内陸の敵陣奥深くに侵入することとなり、その地理に詳しい者も少なく、危険が多い。征服したばかりのラングドック地方を足がかりにするとは言え、そこもまた安全とは言い難い土地ですからね」

「宣戦布告と同時に全軍でラングドック地方から侵入しますが、中央の制圧部隊を囲むようにして十分な兵を用意した制圧部隊を配置し、どこから反撃されても対応できるようにしておくことが必要です」
「うむ――十分に注意して、対応を頼む。ここからが本当の戦いだ」
1140年6月11日。
プロヴァンス戦役終結からわずか1ヶ月で、イスバーニャ帝国軍はフランス王国へと侵攻を開始する。
事前にイーサが計画した通り、全軍を広く展開し、警戒体制を保ちつつ包囲を進行させていく。

自分たちの土地から遠く離れた敵地内でのこの警戒体制は兵士たちの精神を少しずつ磨り減らすものとなっていた。むしろ敵軍が襲いかかってきてくれた方が気が昂り士気も持続できるものだが、半年間以上動きがない中で、制圧は順調に進んでいるとはいえ、兵士たちの中の不安だけが膨れ上がっていく。
そんな中、ついに動きがあったのが1141年2月。南部ミヨーを包囲中のフェルナンドス将軍の部隊の近辺に、突如敵軍が現れたのである。

真冬のタルン川を挟んで対峙するフランス・イスバーニャ両軍。フェルナンドス将軍はすぐさま近隣の味方の部隊に増援を要請する。彼は歴戦の老将であり、無理攻めの愚かさを十分に理解していた。

だが、そこでフランス軍は踵を返し、その場を離れようとする。

これを見て、将軍に突撃を迫ったのが、部隊中の若い将兵たちであった。
そして彼らは将軍を説得するべく、この最も後方に位置し安全とみなされていた部隊に配置されていた皇太子イスマイールを擁立した。

「――殿下。ご理解下さい。精強なる我々イスバーニャ軍は確かに異教徒たちに敗れることはないでしょう。しかしそれが故に、無駄な犠牲を認めるわけにはいきません。兵数は互角、その上で森の中に退避しようとする敵軍に対し、冬の渡河を要する不利な戦いを仕掛けることは、無用な犠牲を生み出すこととなります」
「無用? そんなことはない。この消極策が故に敵を逃してしまえば、それこそここまでの兵たちの苦難が全て無駄となりうる。これは千載一遇の好機である。ここで敵兵主力を捉え殲滅させることで、現在の兵たちが直面している不安の解消に繋がるのだ。そのために、多少の犠牲はやむなしと、兵たちは考えている。前途有望たる若兵たちが皆その命を擲つ覚悟を持っているというのに、熟練たる将軍がそのような弱腰では、兵たちの心も離れてしまうのではないか」

知ったような口を聞く若き将軍の言葉に老兵の心中は困惑で満たされるも、ぐっと堪えて説得を試みる。
「敵兵は敵総兵力に対しても少数。これは我々の包囲網全体に対する牽制であり、囮であるのは間違いありません。ここで我々が陣形を崩せば、そこを狙って敵軍が別のところから仕掛けてくることでしょう」
「もういい――我が全軍を指揮し、これを撃退する」
そう言うとイスマイールは踵を返し、陣幕を出ようとする。フェルナンドスは聞こえぬよう小さく嘆息し、すぐにその背中に声をかける。
もはや、やるしかない。犠牲を覚悟で敵兵を足止めし、後詰めの到着を待つ。
「殿下。承知致しました。私が間違っておりました。責任を持って私が全軍を指揮し、逃げる敵兵を打倒いたします」
1141年2月4日。
フェルナンドス将軍の指揮の下、冷たい真冬の川を越え、4,600のイスラーム兵たちが一気にナヴァセルの森へと突入する。

これを迎え撃つのは、若くしてこの決死隊を率いることを志願したティエール伯アルノールト。4年前、戦場にて病で亡くなった父の誇りを受け継ぐべく、全滅を覚悟でこの場所を守り切るつもりでいた。

「――愚かな。所詮は蛮族の群れ。我々は死ぬのは怖くはないが、一人でも多く、道連れにしてやろうではないか」
「そうだな、将軍」
アルノールトの言葉に同調するのは、モンタルジ伯のジョスラン。武勇の誉れ高い騎士の一人であり、彼もまた死を覚悟してこの部隊への参加を志願していた。

「たとえ最終的に我々が敗北に至るとしても、我々の聖なる土地に足を踏み入れたことを後悔させてやる」
ジョスランは歯を剥き出しにして獰猛に笑う。彼らの元に、イスラーム軍の接近を知らせる伝令が到着し、いよいよ、その時がやってきた。
1141年2月8日。
「ナヴァセルの戦い」が幕を開ける。
数的・地形的不利に見舞われたイスラーム軍だが、それでもフェルナンドスの巧みな指揮の下、敵兵を着実に削っていき、数的不利も覆していく。


「――やはり軟弱なる異教徒軍は恐るるに足らず。我らの武勇を見せつけてやるぞ」
勝勢に気分をよくしたイスマイールは配下の兵たちを束ね、突撃の準備を開始する。
「殿下、深追いは禁物です。勝利は確実、必要以上の犠牲を出すことはなりません」
フェルナンドスが諌めようとするも、イスマイールはこれを一蹴する。
「まだ言うか――良いか、フェルナンドス。私はこの戦いで、何かを成し遂げる必要がある。我が父の偉大さを見よ。そして、イーサ元帥を始めとする、その優秀な指揮官たちを。このまま何事もなくこの戦役を終えてしまえば、私は何者でもないお飾りの皇太子として平和な時代を迎えることとなる。そうなれば、父亡き後、果たして私はこの帝国を治めることなどできるだろうか?
元より私は軍事以外に生きる道はない。この『最後の戦い』で何かを成し遂げられないくらいならば、戦場で散る方が本望である」

イスマイールの真剣な眼差しと言葉にフェルナンドスも思わず返答に窮する。それを見てイスマイールは無言で馬を走らせ、突撃を敢行したのである。

だが、その前に立ちはだかったのが、モンタルジ伯ジョスラン。彼は突撃してきた皇太子の部隊に罠を仕掛け、自ら槍を持ってこれに襲いかかった。

傷つき、馬から崩れ落ちるイスマイール。
そこに、イスラームの精鋭部隊が姿を現した。
「殿下――ご無事か!」

帝国軍最強の将軍たるイーサが自ら先頭に立って戦場に姿を現す。その威容と配下の精鋭兵たちの活躍で次々と敵兵は討ち倒されていき、ついには勝利を掴むこととなった。

結果はイスラーム軍の圧勝。ここでもアブドラールによる追撃が戦果を上げ、敵兵の3分の2を討ち取るか捕虜にすることに成功したのである。

さらに援軍としてやってきたイーサ元帥の部隊が合計で100名以上の敵兵を討ち取るなど大活躍。イスマイールは目の前で格の違いを見せつけられることとなった。

「殿下、傷の具合は大したことはないようで、安心致しました」
イーサの言葉に、イスマイールは羞恥を押し隠すかのように沈黙する。無謀な戦いを行い、結果として元帥に助けられ、自身の栄誉を知らしめるどころかその真逆の結果となり、名誉の死を遂げることすらできずにいる。そのことに、イスマイールは絶望に近い思いを抱いていた。
そんな若者の機微を察し、イーサは優しく声をかける。
「殿下。もし可能であれば、この後の私の軍事行動にご同行頂きたい」
「――何?」
思いがけぬ提案に、イーサは驚きと疑念とを表情に浮かべて元帥を見返す。元帥の軍に同行となれば、それは最も危険で重要な戦いということを意味する。
「我々が今回、このナヴァセルの戦いを敢行している間、制圧軍の最北端に位置していたグティエレの部隊が、突如現れたフランス軍によって襲われたようなのです」

「ただ、これは我々の狙い通りです。元よりグティエレは、我々の軍門に降りながらも改宗を拒んでいた男。今回も、最も危険な最前線の包囲を行わせ、囮とさせた経緯もあります」

「これに誘い出されて敵がやってきた形です。ここに、我々が全速力で襲いかかる」
「なるほど」
元帥の意図をイスマイールは理解した。
「もちろん、行軍速度重視のこの強襲では、兵の準備が万端とは言えないなかで敵に仕掛けるリスクはあります。殿下、それでもご参加なされますか?」
「もちろんだ」
イスマイールは迷う素振りもなく頷く。
「勇敢と無謀も履き違えることなく、今度こそ確実に戦果を出してみせる」
1141年4月。
フランス王国が雇用した傭兵隊「鉄腕隊」を率いるジョフロワの部隊がリムーザンの地でグティエレ軍を強襲。これを敗走させる。


だがこれを、今度は全力で北上してきたイーサの先遣部隊が襲撃。


最初は少数からの襲撃であったが、何とか逃れようとする敵軍を包囲し、着実に削っていく。


やがて遅れて援軍も合流し、形勢は一気に帝国軍側優勢に。

イスマイールもまた、この戦いの中で敵将を負傷させるなど、活躍を見せた。

そして5月10日。この「ラ・マルシュの戦い」はイスラーム軍の圧勝に終わり、鉄腕隊1,800の兵を壊滅させる。


その後反撃に出てきたフランス兵をカルラの戦いで打ち破ったことにより、フランス軍の抵抗戦力はほぼ枯渇する形に。

そのことを把握したイーサは、さらなる大胆な戦略を皇帝に提言する。
「陛下、このまま主力軍を敵首都パリに向けて進軍させられます。そのままヨーロッパの王を恐怖に陥れ、我々の支配を確立する好機となります」
ワハブはこれを承認。帝国軍はパリに進軍し、これを包囲。

フランス王ジャスペールはついに降伏を受け入れ、帝国に臣従。ここにイスバーニャ帝国「征服王」ワハブによるヨーロッパ侵略は大いなる達成を見ることとなったのである。


「お見事で御座います、陛下」
フランス中心部、パリの王宮に足を踏み入れたワハブは、宰相トーマスに感嘆と共に迎え入れられる。
「ついに我々は長きに渡る異教徒への復讐を果たすことができました。この偉業は瞬く間にヨーロッパ中に広がり、我々の信仰の正しさを広めることとなるでしょう」


「うむ――」
宰相の言葉に、ワハブは満足気に頷く。
「ここからが、我々の真の戦いの始まりだ。かつて、ムアーウィヤから始まる大帝国が築きし世界最大の帝国。その限界を我々は超えることに成功した」

「それは、我々の信仰だからこそ、成し遂げられたことだ。遠きマシュリクの地で生まれたアラビア人の信仰が、その勢力の拡大に合わせ北アフリカの先住民ベルベル人たちの中を通り抜け、イベリア半島で『混血』し生まれた我らが信仰*1。だからこそそれは、ピレネーの先、かつての限界のその先にまで到達することができたのである」

「かつて、陛下はこの信仰における矛盾について説いておられましたな」
「うむ――共同体を守るための排他性と適応性を共に併せ持つ、この信仰における大いなる矛盾。然りと否。これこそが、この信仰の無限の可能性を生み出す原動力であった」


「だが――それは、そう簡単に受け入れられるものではない。矛盾を矛盾のままに飲み込むことは、決して簡単なことではないのだ。
故に、単純さを突き詰めようとする旧き信仰の民は、永く抵抗を続けることとなるだろう」
「――陛下」
ワハブの言葉を証明するかの如く、険しい顔をした元帥が玉座の間にやってきた。
「神聖ローマ帝国皇帝アルヌルフおよびイングランド王リチャードが同盟を結び、我々に対して宣戦布告なしの侵攻を開始しました*2」


「敵軍の総兵力は1万7千超。立て続けの戦争にて兵力を減らしている我々を大きく上回る状況です」


「そうか」
報告を受けたワハブは落ち着いた様子で応える。
「マグリブとヒラールのアミールに支援要請を送れ。これはキリスト教徒たちに対するイスラーム全体の聖戦であり、宗派の壁を乗り越えてこの難局を乗り越えぬ限り、両者の争いは永劫に続くことになるであろう、と」
「は――」
ワハブの命に宰相トーマスは頷き、踵を返して部屋を出ていく。
「元帥。援軍が来るまでの間、我々はこの奪い取ったばかりの異教徒たちの大地を守りきらねばならぬ。できるな?」
「もちろんで御座います、陛下。イスマイール殿下と共に、我らが正義の頑強さを異教徒たちに見せつけてやります」
イーサの言葉に、ワハブはにやりと笑った。
「それでこそだ――むしろこれは、好機と捉えねばならぬ」

「この戦いこそ、我らの真の征服のための序章となるであろう。矛盾を受け入れぬ、頑迷なる旧き信仰は新なる正義の信仰の前に敗北する。それは、永きにわたる我々の偉大なる殉教者たちへの弔いとなるであろう」

「キリスト教徒の皇帝を敗北せしめ、イングランドの首都に上陸し、これを制圧せよ! 我々こそが世界の解放者であり、この大地における最強の征服者である!」
ワハブの声と共に、兵士たちは沸き立つ。
彼らは新たな王、新たな皇帝の誕生に、歓喜していた。
何しろその王とは、かつて戦国の時代であったアル=アンダルスに、勝利と統一をもたらした狼王の末裔であり、そしてその原点たる「勝利者」アル=マンスールの末裔であるのだから。
「我々は勝利する! それこそが、我々の定められし栄光であり、そしてこの世の法である! ――かくて法は守らるるべし」

物語は、これでひとまずの終わりを迎える。
その先にあるのが果たして永遠の繁栄か、それとも泡沫の夢に過ぎぬのか。
その真実は、はっきりと語られることは決してないであろう。
だが、この物語において、史実にはありえなかったその可能性の一端を感じ取って頂けたのであれば、幸い。
いつかまた、どこか別の物語にて、会いましょう。
アル=マンスールの一族、完。
アンケートを作りました! お気軽に投票・記載ください!
過去のCrusader Kings Ⅲプレイレポート/AARはこちらから
北条高広の野望β ~上杉謙信を3度裏切った男~北条高広の野望β ~上杉謙信を3度裏切った男~(1567-1585):Shogunate Beta版プレイ。単発。
明智光秀の再演(1572-1609):Shogunateプレイ第4弾。信長包囲網シナリオで、坂本城主・明智光秀でプレイ。その策謀の力でもって信長と共に天下の統一を目指すはずが、想像もしていなかった展開の連続で、運命は大きく変化していく。
江戸城の主(1455-1549):Shogunateプレイ第3弾。「享徳の乱」シナリオで関東の雄者太田道灌を中心とし、室町時代末期から戦国時代中期までを駆け巡る。
正義と勇気の信仰(867-897):アッバース朝末期の中東。台頭するペルシア勢力や暗躍する遊牧民たちとの混乱の狭間に、異質なる「ザイド教団」とその指導者ハサンが、恐るべき大望を秘め動き出す。
織田信雄の逆襲(1582-1627):Shogunateプレイ第2弾。本能寺の変直後、分裂する織田家を纏め上げ、父の果たせなかった野望の実現に向け、「暗愚」と称された織田信雄が立ち上がる。
「きつね」の一族の物語(1066-1226):ドイツ東部シュプレーヴァルトに位置する「きつね」の紋章を特徴とした一族、ルナール家。数多もの悲劇を重ねながら七代に渡りその家名を永遠のものとするまでの大河ストーリー。
平家の末裔 in 南北朝時代(1335-1443):Shogunateプレイ第1弾。南北朝時代の越後国に密かに生き残っていた「平家の末裔」による、その復興のための戦い。
イングランドを継ぐもの(1066-1153):ウィリアム・コンクェスト後のイングランド。復讐を誓うノーサンブリア公の戦いが始まる。
モサラベの王国(867-955):9世紀イベリア半島。キリスト教勢力とイスラーム勢力の狭間に息づいていた「モサラベ」の小国が半島の融和を目指して戦う。
ゾーグバディット朝史(1066-1149):北アフリカのベルベル人遊牧民スタートで、東地中海を支配する大帝国になるまで。